2025年04月の記事
2025 04/18 16:25
Category : 日記
「釧路学Ⅰ 地域 文化 創造」 釧路湿原シニア大学第11期第4講座250422

1)“地域が文化を創る” 外発誘因による官民投資依存型経済 米屋孫右衛門家
https://plaza.rakuten.co.jp/pacific0035/diary/202503300000/ 250407
2)“地域で文化を創る” 軍馬&産業用馬生産に適地適作農業 神八三郎家 250407
https://plaza.rakuten.co.jp/pacific0035/diary/202503310000/#goog_rewarded
3)“地域を文化で創る” 国指定天然記念物・春採湖ヒブナ生息地 371225
https://plaza.rakuten.co.jp/pacific0035/diary/202504110000/
4)釧路方式 釧路ブランドの付加価値~意味・意義創出~
https://plaza.rakuten.co.jp/pacific0035/diary/202504130000/
●釧路方式 高齢者講座の三要素 共に創造、地域に語り部を育てる
※「「(シニア大学・大学院を)運営する理事及び委員、事務局員は、大学及び大学院の卒業生並びに大学当該生から選ばれた者で組織し、ボランティア精神に基づき自主的な運営を行う」
※毎月2回、二講座開講し、班別に運営する「団体動員公民館型生涯学習」&自治会クラブ活動で班組織を超えて自主活動する「個別自主参加図書館型生涯学習」で「学びの多様化を図る」
※シニア大学本科2年で「市民カレッジ学士」、大学院専攻科2年で「市民カレッジ修士」らの称号

1)“地域が文化を創る” 外発誘因による官民投資依存型経済 米屋孫右衛門家
https://plaza.rakuten.co.jp/pacific0035/diary/202503300000/ 250407
2)“地域で文化を創る” 軍馬&産業用馬生産に適地適作農業 神八三郎家 250407
https://plaza.rakuten.co.jp/pacific0035/diary/202503310000/#goog_rewarded
3)“地域を文化で創る” 国指定天然記念物・春採湖ヒブナ生息地 371225
https://plaza.rakuten.co.jp/pacific0035/diary/202504110000/
4)釧路方式 釧路ブランドの付加価値~意味・意義創出~
https://plaza.rakuten.co.jp/pacific0035/diary/202504130000/
●釧路方式 高齢者講座の三要素 共に創造、地域に語り部を育てる
※「「(シニア大学・大学院を)運営する理事及び委員、事務局員は、大学及び大学院の卒業生並びに大学当該生から選ばれた者で組織し、ボランティア精神に基づき自主的な運営を行う」
※毎月2回、二講座開講し、班別に運営する「団体動員公民館型生涯学習」&自治会クラブ活動で班組織を超えて自主活動する「個別自主参加図書館型生涯学習」で「学びの多様化を図る」
※シニア大学本科2年で「市民カレッジ学士」、大学院専攻科2年で「市民カレッジ修士」らの称号
2025 04/17 10:23
Category : 記録
「潜在意識を変化させるスキル」研究、と 「ヒューニング学」の意図250415

250415付で「いとうまい子、60歳で大学教授に “ヤラセ”や“性接待”など芸能界での苦い記憶を明かす」の記事がネット配信。
なかに「ヒューリング学」なる領域の講義が開設されている、と。
そこで「ヒューリング学」とは、なにか。調べてみたが。
東京都武蔵野市にある会社の社長が立ち上げ、起票として立ち上げたらしい。
ヒューニングとは『ヒューマン(人間)』と『チューニング(調律)』を組み合わせた造語。
そう定義し、「弊社=株式会社ヒューロラボ 東京都武蔵野市関前2丁目30番14号 提唱」と説明がある。
なんぞや。
「『潜在意識を変化させるスキル』を研究し、原理原則を導き出し、最も効果のある活用方法を模索」と解説がある。
ご理解いただけるかしら。世に「潜在能力の可視化」とは、申してきたのだが。
起業はその普及のため「コーチング」研修を通じ、トレーナーの養成をめざす。
「(ヒューニング学は)全く新しい学問&世界中の天才たちが作り出したしてゆく学問」。
マスターすることで、「世界中の天才」になれるかも。
因みに『潜在意識を変化させるスキル』には、「催眠、瞑想、セラピー、NLPなど」ばかり、ではない。
幼いころ経験。「(日本の)の板割り、火渡り」、「ハワイのホ・オポノポノなど」も含まれるのだそうだ。

250415付で「いとうまい子、60歳で大学教授に “ヤラセ”や“性接待”など芸能界での苦い記憶を明かす」の記事がネット配信。
なかに「ヒューリング学」なる領域の講義が開設されている、と。
そこで「ヒューリング学」とは、なにか。調べてみたが。
東京都武蔵野市にある会社の社長が立ち上げ、起票として立ち上げたらしい。
ヒューニングとは『ヒューマン(人間)』と『チューニング(調律)』を組み合わせた造語。
そう定義し、「弊社=株式会社ヒューロラボ 東京都武蔵野市関前2丁目30番14号 提唱」と説明がある。
なんぞや。
「『潜在意識を変化させるスキル』を研究し、原理原則を導き出し、最も効果のある活用方法を模索」と解説がある。
ご理解いただけるかしら。世に「潜在能力の可視化」とは、申してきたのだが。
起業はその普及のため「コーチング」研修を通じ、トレーナーの養成をめざす。
「(ヒューニング学は)全く新しい学問&世界中の天才たちが作り出したしてゆく学問」。
マスターすることで、「世界中の天才」になれるかも。
因みに『潜在意識を変化させるスキル』には、「催眠、瞑想、セラピー、NLPなど」ばかり、ではない。
幼いころ経験。「(日本の)の板割り、火渡り」、「ハワイのホ・オポノポノなど」も含まれるのだそうだ。
2025 04/15 09:53
Category : 技術
2024年6月。採点をしながら思わず息を呑んだ。
15問の4選択肢から正答を選ぶ問題で、<9問は正答を>の願い空しく8問が正解。
合格点数不足分を記述問題で救済を。そんなこと考え、解答用紙に目をやると蘭は空白。

1999年に立ち上げたわけだから、四半世紀を経たわけだが自治体史の取りまとめに召しだされている。
往時、喜寿・古希に前後する方は、せっせと筆をすすめてくださった。
当時、現役世代であったかたも次第に、古稀・還暦のハードルを越えられたが、目下散々に、ご苦労をいただいている。
違いはなんぞや。そんな思いがめぐらすなか、25年4月11日。『東洋経済オンライン』版で、『読解力は最強の知性である』より一部抜粋・編集の記載を読んだ。
7つの要因が解説されている。さらに、抜粋してここに紹介してみる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c18e1bce6d8ac543fd914d2d61297fc4876fff03
■本は読解力を養う「超実践の場」
①読書量の低下
②会話量の低下
③スマホの受動的使用【思考停止】
■一見便利な「思考しなくてもよい生活」の危険
④認知機能の低下
■読解力と認知機能の関係は、切っても切り離せない。
⑤個人が書くチャット&SNSの文章に触れる機会の増加
⑥世代間コミュニケーションの減少
⑦アウトプット不足
■借り物ではない「自分の言葉」でアウトプットを
「記述問題の解答欄」を<空白>で提出の若者に、伝えた点。
⑧積極的に家事を分担、努めて地域での住民活動にも参加。
⑨夕食を共に過ごし家族とのコミュニケーション、叔父・伯母・イトコたちの話題を日常化。
⑨寝る前の一定時間<Text以外の本を読む>を日課に、できれば<読んだあとの一筆>めざす。
されば、「習った記憶がなくても、なにかを、なんとか、書くことできる」。
かく申しつつ、「習っていないのではない」&「わすれたのではなく」、「なんとか書くこと出来る一文が浮かぶ」。
15問の4選択肢から正答を選ぶ問題で、<9問は正答を>の願い空しく8問が正解。
合格点数不足分を記述問題で救済を。そんなこと考え、解答用紙に目をやると蘭は空白。

1999年に立ち上げたわけだから、四半世紀を経たわけだが自治体史の取りまとめに召しだされている。
往時、喜寿・古希に前後する方は、せっせと筆をすすめてくださった。
当時、現役世代であったかたも次第に、古稀・還暦のハードルを越えられたが、目下散々に、ご苦労をいただいている。
違いはなんぞや。そんな思いがめぐらすなか、25年4月11日。『東洋経済オンライン』版で、『読解力は最強の知性である』より一部抜粋・編集の記載を読んだ。
7つの要因が解説されている。さらに、抜粋してここに紹介してみる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c18e1bce6d8ac543fd914d2d61297fc4876fff03
■本は読解力を養う「超実践の場」
①読書量の低下
②会話量の低下
③スマホの受動的使用【思考停止】
■一見便利な「思考しなくてもよい生活」の危険
④認知機能の低下
■読解力と認知機能の関係は、切っても切り離せない。
⑤個人が書くチャット&SNSの文章に触れる機会の増加
⑥世代間コミュニケーションの減少
⑦アウトプット不足
■借り物ではない「自分の言葉」でアウトプットを
「記述問題の解答欄」を<空白>で提出の若者に、伝えた点。
⑧積極的に家事を分担、努めて地域での住民活動にも参加。
⑨夕食を共に過ごし家族とのコミュニケーション、叔父・伯母・イトコたちの話題を日常化。
⑨寝る前の一定時間<Text以外の本を読む>を日課に、できれば<読んだあとの一筆>めざす。
されば、「習った記憶がなくても、なにかを、なんとか、書くことできる」。
かく申しつつ、「習っていないのではない」&「わすれたのではなく」、「なんとか書くこと出来る一文が浮かぶ」。
2025 04/14 10:47
Category : 記録
環境にやさしく、分断・対立・闘争さけて災害にも“したたか” 地域を文化で創る=国指定天然記念物・春採湖ヒブナ生息地371225

昭和12年。師走の25日に国は「春採湖ヒブナ生息地」を天然記念物に指定した。
指定理由に申す。
「春採湖ハ上層ニ過飽和ノ酸素ヲ含ミ下層ニハ之ヲ缺ク珍奇ナル湖ニシテ往古ヨリ多クノ緋鮒ヲ産ス緋鮒ハ鯡ノ紅化セルモノニシテ本棲息地ハ我國有數ノモノナリ」。
ヒブナが国の天然記念物に指定されたわけではないが、その生息地とたる春採湖が人間の手で現状を変更することに、ストップがかかったのだ。
指定の時点までに、湖畔一帯は人手を加えられた。なにしろ釧路炭田を代表する炭鉱の、採炭坑口、選炭場、港口輸送路、住宅街。
湖畔の陸地は埋立てられていた。特に南西口では失業対策事業で、城山地区の丘陵をくすし、湖畔の埋め立てにあてていた。
水泳プールを思わせる湖の水際線には、その記憶を重ねねばならない。人口急増で宅地が不足。
ただ、それ以上に時代は急激に動いていた。
31年9月 柳条溝事件で日本軍は中国大陸に非常時を拡大。釧路港から大陸に送られる貿易量は増加。
とりわけ石炭は、その生命線でもあった。事実、石炭統計をみるとその出炭量は41年にむけ戦前ピークを記録していた。
「石炭増産にノー」とは、とてもとても言えない時代。春採湖の環境を保全する<知恵>が天然記念物の国指定であった。
そうするならば、時代にあらがうことが出来ない世相をシッカリ見きわめ、「ノートはいわずに、持続利用を実現」。
これぞ、「地域を文化で創る」の典型例ではないか。時代と時代、時代と人、人と自然を見事に、つないだ。

昭和12年。師走の25日に国は「春採湖ヒブナ生息地」を天然記念物に指定した。
指定理由に申す。
「春採湖ハ上層ニ過飽和ノ酸素ヲ含ミ下層ニハ之ヲ缺ク珍奇ナル湖ニシテ往古ヨリ多クノ緋鮒ヲ産ス緋鮒ハ鯡ノ紅化セルモノニシテ本棲息地ハ我國有數ノモノナリ」。
ヒブナが国の天然記念物に指定されたわけではないが、その生息地とたる春採湖が人間の手で現状を変更することに、ストップがかかったのだ。
指定の時点までに、湖畔一帯は人手を加えられた。なにしろ釧路炭田を代表する炭鉱の、採炭坑口、選炭場、港口輸送路、住宅街。
湖畔の陸地は埋立てられていた。特に南西口では失業対策事業で、城山地区の丘陵をくすし、湖畔の埋め立てにあてていた。
水泳プールを思わせる湖の水際線には、その記憶を重ねねばならない。人口急増で宅地が不足。
ただ、それ以上に時代は急激に動いていた。
31年9月 柳条溝事件で日本軍は中国大陸に非常時を拡大。釧路港から大陸に送られる貿易量は増加。
とりわけ石炭は、その生命線でもあった。事実、石炭統計をみるとその出炭量は41年にむけ戦前ピークを記録していた。
「石炭増産にノー」とは、とてもとても言えない時代。春採湖の環境を保全する<知恵>が天然記念物の国指定であった。
そうするならば、時代にあらがうことが出来ない世相をシッカリ見きわめ、「ノートはいわずに、持続利用を実現」。
これぞ、「地域を文化で創る」の典型例ではないか。時代と時代、時代と人、人と自然を見事に、つないだ。
2025 04/06 10:25
Category : 社会
外発誘因による官民投資依存型経済 “地域が文化を創る”米屋孫右衛門家
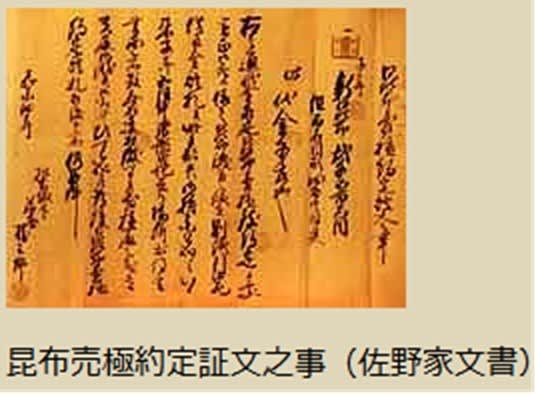
戦国時代、“朝鮮征伐”の代償を払った秀吉・家康政権は、南の琉球と北の蝦夷地に植民地を用意した。
対アイヌ民族。自然採集経済を生業とする地域に、投資せずして得分を手にする対マイノリティ&本州側商品との“交易”を通じた従属関係を組み立てた。
時代はうつり、対中国貿易赤字・畿内農産品増産・対ロシア脅威を背景に、資本・生産手段・出稼ぎ労働力を投入する“漁業経営”を独占する経済システムに移行した。
蝦夷地産品の産地とその消費市場を結節するのは、資本力を有する本州側商人。
豊富な資金、消費&生産の品を輸送する廻船手段、生産地港と消費地港のそれぞれ問屋を仲介して、流通・販売ルートを独占した。
母村から漁場まで旅賃を前借、漁場での衣食住+生産手段込みで借用して、仕事納めに“稼ぎ高”を精算。当然、元本のほかに高利息が伴う。
当然、漁獲物の買い取り価格も商人側が設定する、従属形態。
良いの、悪いの。かく申しても商人がバックにする流通・販売ルートに乗せて、初めて価値を産む。
本州農村に滞留する“裸一貫の農民”。今日的に申すと“日払いバイト”。
因みに「日払いバイト」とは、「即日勤務も可能。高時給・高収入な短期バイトや即日払いの単発バイト」。
結果。域外商人の資本・技術・価格設定=外発誘因、新鮮漁獲物の付加価値形成。
そして成果品=商品は、政権・諸湊問屋・仲介商人=官民投資依存型経済。
この枠組みで、北海道は近世・近代を“本州経済の補完”機能で位置することに。
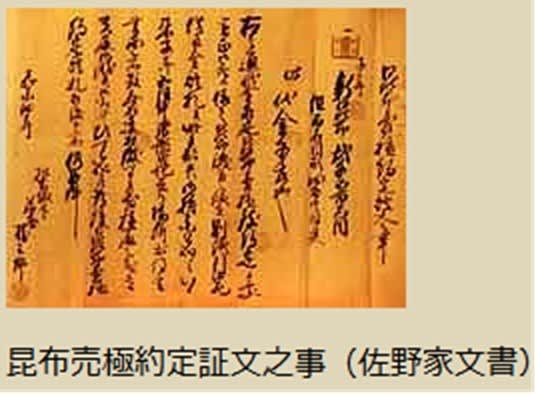
戦国時代、“朝鮮征伐”の代償を払った秀吉・家康政権は、南の琉球と北の蝦夷地に植民地を用意した。
対アイヌ民族。自然採集経済を生業とする地域に、投資せずして得分を手にする対マイノリティ&本州側商品との“交易”を通じた従属関係を組み立てた。
時代はうつり、対中国貿易赤字・畿内農産品増産・対ロシア脅威を背景に、資本・生産手段・出稼ぎ労働力を投入する“漁業経営”を独占する経済システムに移行した。
蝦夷地産品の産地とその消費市場を結節するのは、資本力を有する本州側商人。
豊富な資金、消費&生産の品を輸送する廻船手段、生産地港と消費地港のそれぞれ問屋を仲介して、流通・販売ルートを独占した。
母村から漁場まで旅賃を前借、漁場での衣食住+生産手段込みで借用して、仕事納めに“稼ぎ高”を精算。当然、元本のほかに高利息が伴う。
当然、漁獲物の買い取り価格も商人側が設定する、従属形態。
良いの、悪いの。かく申しても商人がバックにする流通・販売ルートに乗せて、初めて価値を産む。
本州農村に滞留する“裸一貫の農民”。今日的に申すと“日払いバイト”。
因みに「日払いバイト」とは、「即日勤務も可能。高時給・高収入な短期バイトや即日払いの単発バイト」。
結果。域外商人の資本・技術・価格設定=外発誘因、新鮮漁獲物の付加価値形成。
そして成果品=商品は、政権・諸湊問屋・仲介商人=官民投資依存型経済。
この枠組みで、北海道は近世・近代を“本州経済の補完”機能で位置することに。
2025 04/05 15:43
Category : 記録
鷲は弓矢の羽。鷹は鷹狩りにもちいられた。
鷹の主要産地は津軽・南部・松前の東北、北海道の3藩が代表であった。
鷹は最高権力の象徴であった。だから優れた鷹を厳重な管理のもとに、輸送し将軍家に献上するものである。
シラヌカ場所 91年(寛政3年)にも飛内儀右衛門持(東蝦夷地道中記)。
「蝦夷商賈聞書」によれば出物はトカチ場所と同様干鮭などで、塩鶴はないという。
掲載図は【タンチョウの生け捕り】(『蝦夷風俗図』函館市立図書館所蔵=「クスリ商場の開設」 『釧路昔むかし 釧路歴史散歩』)
https://www.hokkai.or.jp/history/kusiro-mukasi/1-3.html

「軽物 かるもの」の名があった蝦夷地交易品 その用途 鷹・鷲250405
鷹の主要産地は津軽・南部・松前の東北、北海道の3藩が代表であった。
鷹は最高権力の象徴であった。だから優れた鷹を厳重な管理のもとに、輸送し将軍家に献上するものである。
シラヌカ場所 91年(寛政3年)にも飛内儀右衛門持(東蝦夷地道中記)。
「蝦夷商賈聞書」によれば出物はトカチ場所と同様干鮭などで、塩鶴はないという。
掲載図は【タンチョウの生け捕り】(『蝦夷風俗図』函館市立図書館所蔵=「クスリ商場の開設」 『釧路昔むかし 釧路歴史散歩』)
https://www.hokkai.or.jp/history/kusiro-mukasi/1-3.html

「軽物 かるもの」の名があった蝦夷地交易品 その用途 鷹・鷲250405
2025 04/04 15:53
Category : 地域
選良。聞きなれぬか、選挙で選ばれた人=転じてエリートのこと。
1 仕事があるから集まって来たマチ。今度は集まって来た人が雇用をつくる。
2 炭鉱が閉山した。炭鉱に代わる雇用を創出しなければいけない。
3 少子高齢化の時、人口減を防ぐために、まず経済政策。

地域の時代画期ごとに識者は、さまざまな処方箋を示してくれた。1)~3)はその代表例。
なかには高額か否かは別にして、講演報酬や調査費用も負担した例も含まれる。
1)は1978年、前年の国際漁業規制、つまり200海里問題をうけての処方。
2)は創業82年の坑内掘り炭鉱が閉山し、直轄1000人、下請け500人余の雇用が喪失した時。
3)は日本製紙(株)釧路工場の抄紙部門が停止したあとの市長選挙を前に、
道内配布紙の支社報道部記者が、記事にしていた一行。
読んだ読者、市民。一様に思うようだ。
「雇用創出」「経済政策が大事」。それは十分に承知している。「知りたいのは、その具体的内容、それが見つからずに困っている」。
そういうことではないか。
で、その答えは?。多くの人が、「あなたは、<わが事>として、なにを?」。「そこ教えて」。
3)の取材で聞かれたとき、筆者は3点考えた。
4)「(閉山した炭鉱が跡地を放置した点を念頭に)グリーンニューディールで自然再生」。
5)「(ただ「掘る」「伐る」「獲る」「作る」「搾る」の経済に)自前で価格設定できる付加価値の創出」
6)「外発誘因で生み出した受益を、内発誘因型経済に充当」
記事で扱われたのは4)のみであるも。
1)~3)を語られる選良。私案を示されてはいかが「雇用が、経済が でわ具体策を」。
掲載画像はLINEで頂戴。岐阜県美濃加茂市の桜、と。
1 仕事があるから集まって来たマチ。今度は集まって来た人が雇用をつくる。
2 炭鉱が閉山した。炭鉱に代わる雇用を創出しなければいけない。
3 少子高齢化の時、人口減を防ぐために、まず経済政策。

地域の時代画期ごとに識者は、さまざまな処方箋を示してくれた。1)~3)はその代表例。
なかには高額か否かは別にして、講演報酬や調査費用も負担した例も含まれる。
1)は1978年、前年の国際漁業規制、つまり200海里問題をうけての処方。
2)は創業82年の坑内掘り炭鉱が閉山し、直轄1000人、下請け500人余の雇用が喪失した時。
3)は日本製紙(株)釧路工場の抄紙部門が停止したあとの市長選挙を前に、
道内配布紙の支社報道部記者が、記事にしていた一行。
読んだ読者、市民。一様に思うようだ。
「雇用創出」「経済政策が大事」。それは十分に承知している。「知りたいのは、その具体的内容、それが見つからずに困っている」。
そういうことではないか。
で、その答えは?。多くの人が、「あなたは、<わが事>として、なにを?」。「そこ教えて」。
3)の取材で聞かれたとき、筆者は3点考えた。
4)「(閉山した炭鉱が跡地を放置した点を念頭に)グリーンニューディールで自然再生」。
5)「(ただ「掘る」「伐る」「獲る」「作る」「搾る」の経済に)自前で価格設定できる付加価値の創出」
6)「外発誘因で生み出した受益を、内発誘因型経済に充当」
記事で扱われたのは4)のみであるも。
1)~3)を語られる選良。私案を示されてはいかが「雇用が、経済が でわ具体策を」。
掲載画像はLINEで頂戴。岐阜県美濃加茂市の桜、と。
2025 04/03 13:22
Category : 記録
大佐渡&小佐渡の二島 砂丘がつなぐ国中平野 暖流寒流接点で多様な水産物 佐渡島の自然250403

最近、なにかのTV番組に登場の佐渡島。
「金山の食料をささえた国中平野」と、紹介。俄然、この佐渡島はいかにして形成されたか。
結論は「金北山 H=1172メートル」の大佐渡、「大地山 H=646メートル」の小佐渡。
その二島がくっつき、その間に両津湾と宜野湾が給する砂が堆積して国中平野が発達。
約300万年前。日本列島全体がプレートに押されて隆起を始めると、海底にあった佐渡にも力が加わり、大佐渡、小佐渡が二つの島となって海上に顔を出した。
ところが先立つ約3000万年前の大地をしっかり抱えたまま隆起したおかげで、佐渡島には豊かな金銀鉱脈が存在。
(「二つの島がつながった金の島 水が語る佐渡│ ミツカン 水の文化センター機関誌『水の文化 61号』)
沖合は暖流と寒流が接する。暖流=対馬海流&寒流=リマン海流。
暖流にシイラ、カツオ、アオリイカがのり、寒流にはブリが漁獲される多様性。
植生でも寒地(北方)系・暖地(南方)系の両地方特有の植物が同居する、非常に珍しい植生地域。
生涯学習資源が豊富。つまり魂を揺すぶる出会いとおもてなし、満載。

最近、なにかのTV番組に登場の佐渡島。
「金山の食料をささえた国中平野」と、紹介。俄然、この佐渡島はいかにして形成されたか。
結論は「金北山 H=1172メートル」の大佐渡、「大地山 H=646メートル」の小佐渡。
その二島がくっつき、その間に両津湾と宜野湾が給する砂が堆積して国中平野が発達。
約300万年前。日本列島全体がプレートに押されて隆起を始めると、海底にあった佐渡にも力が加わり、大佐渡、小佐渡が二つの島となって海上に顔を出した。
ところが先立つ約3000万年前の大地をしっかり抱えたまま隆起したおかげで、佐渡島には豊かな金銀鉱脈が存在。
(「二つの島がつながった金の島 水が語る佐渡│ ミツカン 水の文化センター機関誌『水の文化 61号』)
沖合は暖流と寒流が接する。暖流=対馬海流&寒流=リマン海流。
暖流にシイラ、カツオ、アオリイカがのり、寒流にはブリが漁獲される多様性。
植生でも寒地(北方)系・暖地(南方)系の両地方特有の植物が同居する、非常に珍しい植生地域。
生涯学習資源が豊富。つまり魂を揺すぶる出会いとおもてなし、満載。
2025 04/02 15:17
Category : 放送
皮をむいたリンゴ、茶褐色になるように 発酵・萎凋・揉捻と緑茶、烏龍茶、紅茶250402

喫茶は飲酒&喫煙とならぶ暮らしの折り目。
「これぞ、その原稿を書く前には一杯の茶」。人により茶=抹茶、緑茶、コーヒー、紅茶といろいろあれど、も。
250402「世界史の探求 高校講座」の時間に紹介。「緑茶、ウーロン茶、紅茶はいずれも、同じ茶木・茶葉から出来ています」。
そうかー。で、「緑茶=不発酵茶」「ウーロン茶=半発酵茶」「紅茶=発酵茶」の差異。
ところが「注」があった。二点。「発酵=微生物の働きによって物質に(人間にとって有用な)変化が生じること」
しかし、「茶の発酵」は違う、と、「お茶における発酵=茶葉中の酵素の働きにより、葉中のカテキン類が酸化すること」を言うのだそうだ。
お茶の発酵にとって大切な製造工程に「萎凋 いちょう」という作業が行われるのだ、と。
特にウーロン茶=判発酵茶&紅茶=発酵茶の製造に欠かせない大切な工程というのだ。
仕上げに申す。重ねて、その発酵にとってたいせつなことは「必要なことは揉捻 じゅうねんの工程」。
これによって、紅茶ならではの華やかな香りや色合いが生み出される。
う~ん、なかなか奥が深い。おろそかに呑むことなかれ「煎茶一服」。
おさらい:
1)お茶の発酵=茶葉中の酵素の働きにより、葉中のカテキン類が酸化すること。
2)萎凋 いちょう=茶葉中の酵素の働きにより、葉中のカテキン類が酸化すること。
(生の茶葉を放置して萎れさせる工程)(つまり、皮をむいたリンゴに似て、空気にふれると茶色に変色する現象=烏龍&紅茶)
3)揉捻 じゅうねん=酸化酵素が活性化した茶葉に圧力をかけながら揉んで酸化を促進、酸化反応が均一に進むようにする工程
原稿を書く時世話になる茶。心して喫せねば。(図版=健康堂東京 HP)
1)は緑茶・烏龍茶・紅茶に共通するも、2)&3)は紅茶・烏龍茶の製造には欠かせない大切な工程、と。

喫茶は飲酒&喫煙とならぶ暮らしの折り目。
「これぞ、その原稿を書く前には一杯の茶」。人により茶=抹茶、緑茶、コーヒー、紅茶といろいろあれど、も。
250402「世界史の探求 高校講座」の時間に紹介。「緑茶、ウーロン茶、紅茶はいずれも、同じ茶木・茶葉から出来ています」。
そうかー。で、「緑茶=不発酵茶」「ウーロン茶=半発酵茶」「紅茶=発酵茶」の差異。
ところが「注」があった。二点。「発酵=微生物の働きによって物質に(人間にとって有用な)変化が生じること」
しかし、「茶の発酵」は違う、と、「お茶における発酵=茶葉中の酵素の働きにより、葉中のカテキン類が酸化すること」を言うのだそうだ。
お茶の発酵にとって大切な製造工程に「萎凋 いちょう」という作業が行われるのだ、と。
特にウーロン茶=判発酵茶&紅茶=発酵茶の製造に欠かせない大切な工程というのだ。
仕上げに申す。重ねて、その発酵にとってたいせつなことは「必要なことは揉捻 じゅうねんの工程」。
これによって、紅茶ならではの華やかな香りや色合いが生み出される。
う~ん、なかなか奥が深い。おろそかに呑むことなかれ「煎茶一服」。
おさらい:
1)お茶の発酵=茶葉中の酵素の働きにより、葉中のカテキン類が酸化すること。
2)萎凋 いちょう=茶葉中の酵素の働きにより、葉中のカテキン類が酸化すること。
(生の茶葉を放置して萎れさせる工程)(つまり、皮をむいたリンゴに似て、空気にふれると茶色に変色する現象=烏龍&紅茶)
3)揉捻 じゅうねん=酸化酵素が活性化した茶葉に圧力をかけながら揉んで酸化を促進、酸化反応が均一に進むようにする工程
原稿を書く時世話になる茶。心して喫せねば。(図版=健康堂東京 HP)
1)は緑茶・烏龍茶・紅茶に共通するも、2)&3)は紅茶・烏龍茶の製造には欠かせない大切な工程、と。
2025 04/01 09:09
Category : 地域
相当遠慮がち=“私を変えます” 「ガイド候補生続々 釧路 要請・観光講座12人受講」(『釧路新聞)250330一面

釧路観光ガイドの会(木村浩章会長 2002年創立)が主宰の「ガイド養成・観光講座)の第2年次ガイド養成・観光講座が開かれた。
参加者は12名。主宰者も構成会員が圧倒的に80歳台となって居るに対応、若手後継者の発掘・育成に努める、と。
ここ3年。続けてきた「釧路の魅力発見・観光講座」の受講者の中から、さらに意欲ある市民。その参加で二年次目の講座が3日間、修了との報だ。
取材した郷 裕策記者は「活動継続へ育成に力」と小見出しを付け、会社勤めの50歳台女性、神奈川から移住の40歳台女性の声が紹介されている。
3年前、筆者は聞いたことがある。「全市のガイド養成を、ガイドさんの団体が主催するの?」。
返事。「自身は官庁で開催した講座で育った、今や、役所も経済団体も開かない」。
ために後継者供給のパイプや、育つ機会がなくなったのだ、と。続けて。
「で、会員が受け取る日当から一部を天引きして、自前講座開催の運営経費にあてる」と。
2002年に初めてかかわった者として、驚いた点を記載しておきたい。
地域政策では、公共団体も経済団体も声高に「観光、観光!&観光」。
しかし、おいで頂いた客人。受け入れる対策は、人材育成に始まり、貧弱。
そうではないか。「観光=魂を揺すぶる出会いとおもてなし」。その策は、無策にといってもいかが。
ひたすら「来い、来てよ」は、旅行代理店を潤すのみで、いや、それとても<おぼつかなくなる>のかも。
3月30日、市内を中心に配布される紙面のトップ記事をみた。
従事者は尊く、しかしである。その汗で支えられる階層は、いささか“努力不足”かと。
観光=他者の努力で<フトコロ潤す>で票になる。
その行き詰まりに<他者変えられぬ、自身がかわろうと生涯学習>。その尊さに刮目すまいか。

釧路観光ガイドの会(木村浩章会長 2002年創立)が主宰の「ガイド養成・観光講座)の第2年次ガイド養成・観光講座が開かれた。
参加者は12名。主宰者も構成会員が圧倒的に80歳台となって居るに対応、若手後継者の発掘・育成に努める、と。
ここ3年。続けてきた「釧路の魅力発見・観光講座」の受講者の中から、さらに意欲ある市民。その参加で二年次目の講座が3日間、修了との報だ。
取材した郷 裕策記者は「活動継続へ育成に力」と小見出しを付け、会社勤めの50歳台女性、神奈川から移住の40歳台女性の声が紹介されている。
3年前、筆者は聞いたことがある。「全市のガイド養成を、ガイドさんの団体が主催するの?」。
返事。「自身は官庁で開催した講座で育った、今や、役所も経済団体も開かない」。
ために後継者供給のパイプや、育つ機会がなくなったのだ、と。続けて。
「で、会員が受け取る日当から一部を天引きして、自前講座開催の運営経費にあてる」と。
2002年に初めてかかわった者として、驚いた点を記載しておきたい。
地域政策では、公共団体も経済団体も声高に「観光、観光!&観光」。
しかし、おいで頂いた客人。受け入れる対策は、人材育成に始まり、貧弱。
そうではないか。「観光=魂を揺すぶる出会いとおもてなし」。その策は、無策にといってもいかが。
ひたすら「来い、来てよ」は、旅行代理店を潤すのみで、いや、それとても<おぼつかなくなる>のかも。
3月30日、市内を中心に配布される紙面のトップ記事をみた。
従事者は尊く、しかしである。その汗で支えられる階層は、いささか“努力不足”かと。
観光=他者の努力で<フトコロ潤す>で票になる。
その行き詰まりに<他者変えられぬ、自身がかわろうと生涯学習>。その尊さに刮目すまいか。